
僕とOVERCOAT
2022.10.12 / BRAND
僕は、今まであまり誰かに「憧れる」ということがなかった。「憧れる」は「好き」とはちょっと違う。「好き」は無責任に言うことができるが「憧れる」にはそれなりの根拠が必要だ。
「憧れる」とは、いつかその人のようになりたいと思うことだ。だとすれば、自分と憧れの人との間に、何らかの共通点がなければならない。少なくとも、共通点があると思い込んでいなければならない。
だから僕は昔から、簡単に誰かを「憧れる」ことができなかった。僕には「憧れる」なんて傲慢なことを言う自信がなかった。
小学生の頃、少年野球をやっている友達が、「プロ野球選手に憧れる」と言うのを聞くたび、僕はそれをとても羨ましく思っていた。確かに、その友達とプロ野球選手との間には、野球という共通点がある。だから友達はプロ野球選手に「憧れる」ことができる。しかし、その頃の僕は、そういう世の中のヒーロー達と繋がるための共通点を、何ひとつ持っていなかったのだ。
僕はそんなことをぼーっと考えつつ、父親に髪を切ってもらっていた。僕の実家は「カット倶楽部ウッドストック」という名の理髪店を営んでいる。なので幼い頃から僕の髪を切るのは、いつも父親だ。
僕は今まで一度も父親に「誰々みたいな髪型にしてくれ」と言ったことがない。毎回「あと何センチ短く」などと、細かく注文をして切ってもらっている。考えてみれば、そんな面倒なことをしているのも、きっと僕が「誰かに憧れられない」からなのだろう。「誰々みたいな髪型にしてくれ」なんて傲慢なことを、父親にさえ言えなかった。いや、むしろ父親だから言えなかったのかもしれない。
しかし、今回は父親にある人の写真を見せようと決めていた。そのある人とは「OVERCOAT」のデザイナーの大丸さんだった。僕が人生で初めて、自分を似せたいと思った人だ。この人だったら素直に「憧れる」と言える気がする。僕はそう思い、今まで躊躇していた、写真を見せて髪を切ることを決断したのだ。
父親から「お前はその人に憧れてるのか」と聞かれるかもしれないと思うと、何故か急にとても恥ずかしい感じがした。しかし、決めたことだと、父親に恐る恐るスマホの画面を見せた。父親が「誰この人」と聞いてきて、ドキっとしたが、僕はなんとか平静を装い「デザイナー」とだけ言った。父親はそれ以上何も聞いてこなかった。
パーマをあてながら、父親に渡されたファッション誌のページをパラパラとめくる。だが一向に内容は入ってこない。僕はどうしてこんなに大丸さんに憧れているのか、そのことばかり気になって頭の中がいっぱいだった。考えているうちにぼんやりと、中学生の頃の記憶が蘇ってきた。
僕は体が小さく運動神経が無かったので、入部したバスケ部でも完全にお荷物だった。同級生がみんなボールを使った練習をしている中、僕はひとり基礎体力をつけるため、コート脇で腹筋をさせられていた。
休みの日は友達の家に集まってテレビゲームをした。ウイイレやスマブラにみんな夢中だったが、僕はそこでも活躍出来なかった。誰もが僕とチームになると落胆して「もう絶対負けやん」と次々に悪態をついた。運動神経も無い上に、反射神経も人より劣るのだということを、僕はそこで思い知らされたのだった。
今考えれば、その時唯一僕が友達から注目を集めることができたのが、ファッションだったのかもしれない。
僕の家は、ゲームなどの手頃な遊び道具がない家だったので、仕方なく父親が店で不用になり持ち帰ったファッション誌を読んで暇を潰していた。
年齢的にちょうど色気付いてきて、自然とみんなファッションに興味が向き始める時期だった。そんな中、何故かファッションについてちょっと詳しい僕に、みんなが色々と質問してくるようになった。
いつしか僕の「運動もゲームもできないのろま」というイメージに「でもなんかお洒落なやつ」という付加価値がついて、みんなから一目置かれるようになった。それからは部活で失敗して笑われても、むしろ「おいしい」んじゃないかと思えるようになった。
僕みたいなやつでも、面白い事を知っていれば一目置かれる。ダメな部分があっても、それがプラスに転化する。
ファッションというか芸術というか文化というか、そういう類のものが持っている、不思議な力の効力を、僕はその時初めて体感したのかもしれない。
僕はその時から漠然と、ファッションの道に行きたいと思うようになった。しかし、そう思ったところで、具体的にどうしたらいいのか、その頃の僕にはわからなかった。
僕には、ファッションの世界の人達は、プロ野球選手のような典型的なヒーロー達とは全く違って見えた。そんな世の中の基準から外れたヒーローのことを「憧れる」対象にしていいのか自信がなかった。
ファッションは野球と違い「努力している」という実感が持ちにくい。僕がどんなに真剣だろうとも、学校や親からしたら、それは結局遊びでしかない。
僕は、そんな逸れもののヒーロー達と、ファッションという共通点で繋がっているつもりだったが、それを周りの大人達に力強く宣言するだけの自信を、まだ持つことができなかった。
その調子で高校入学後3年間を過ごし、僕は反対する親に無理を言って、服飾の専門学校へ進学することになった。
僕が進学を決めた専門学校には特待生という枠があった。面接の結果次第で、特待生か普通の学生か決まり、特待生になれれば学費の何割かが免除されるという制度だった。
僕はどうしても特待生になりたかった。ここで特待生になることができれば、今まで遊びだと思われていたものが、僕なりの努力だったと証明できるのではないか。そう僕は思ったのだ。
特待生になるためには、面接の場で自主課題の発表を行う必要があった。早速僕は課題に取り組むべく、母親の使わなくなったミシンを押し入れから引っ張り出し、持っていたデニムパンツを解体してバンダナと縫い合わせ作品を作った。
それだけでは心もとなかったので、もうひとつの課題として、思い当たる洋服屋さんにインタビューをして、データベースを作り、ショッピングガイドにして提出しようと思い立った。
意気揚々と街へインタビューに出かけたが、これがなかなか上手くいかなかった。今になって考えればそんなの当然なのだが、客数や客単価や売れ筋などの、社外秘のような情報を、ズケズケと聞いてくるイタい高校生なんて、鬱陶しいに決まっている。ほとんどの店で門前払いをくらい、なんとか話をしてもらえたとしても、叱られることが多かった。
そんな数日を過ごし、ついにリストアップしていた店は最後の一軒になった。その店はダイスアンドダイスだった。
ダイスは僕の中では別格の店だった。「憧れる」なんて軽々しく言えない。それはもはや畏怖するような存在だった。
店構えも働いているスタッフの雰囲気も他とは全然違う。いつも買い物をするだけで汗だくになっていた。
その日も緊張のあまり、店の前を行ったり来たりして、何度もそのまま帰ろうかと思った。
しかし、特待生になるためにはこの試練を超えなければならない。そう自分に言い聞かせて、決死の覚悟で店中へ飛び込んだ。滝のように流れる汗を押さえながら、僕はスタッフの人にインタビューの概要を説明した。
すると意外にも「全然いいよ」と言って快くインタビューを受けてくれた。インタビューだけでなく、親身になって自主課題の相談にも乗ってくれ、最後に「頑張ってね」と声をかけてもらえたのを、今でもはっきりと覚えている。
振り返ると、この時の出来事は僕の人生の中で、とても大切な経験だったように思う。誰から言われるよりも嬉しい「頑張ってね」だった。初めて努力が認められたような感じがした。
少なくとも、いつかこんな店で働いてみたいと、僕が強く思うようになったきっかけであったのは言うまでもない。
僕はやっと完成させた自主課題を持って専門学校の面接の場に挑んだ。結果は不合格だった。
高校の内申点が高くないと特待生にはなれないということを、僕は後から知った。
普通の学生として通い始めることになった専門学校は、どうしても身が入らなかった。今思えば僕が浅はかだったのだろうが、その時は、無意味な声出しや服のたたみ方を、わざわざ学校で学ぶことに、何のリアリティも感じなかった。
僕は親に相談もせず、一年も経たないうちに、学校を辞めてしまった。純粋な憧ればかりを追い求めるあまり、現実が見えなくなって、自分でも収拾がつかなくなっていた。
親と折り合いがつかなくなって、実家に居づらくなり、半年間程ふらふらと公園で寝泊まりする生活を送った。
なんとかなるだろうと思っていたが、実際はなんともならなかった。どうしようもなく腐りかけていた時、知人から急な誘いを受けた。「ダイスで働いてみらん?」僕は二つ返事で「はい」と答えた。
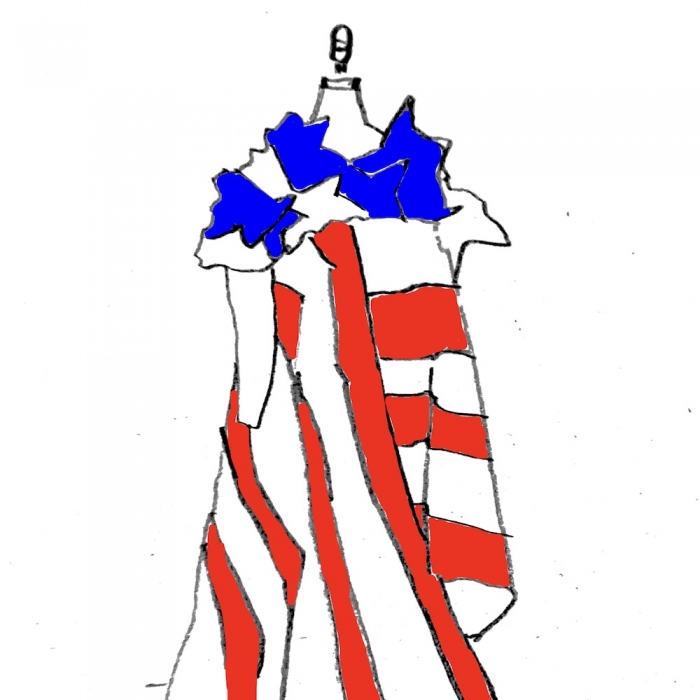
憧れの場所で働き始めてかれこれ10年。その間、僕は沢山の素敵な服と出会った。中でも最も衝撃を受けたのが大丸さんの作る「OVERCOAT 」だった。
「OVERCOAT 」の服を初めて着た時、僕は強烈な違和感を感じた。いつもは窮屈なところに、空間ができていることに気がつく。いつもは沿わないところに何故か生地が沿ってくる。緊張しているところは程よく緩み、逆に緩んでいたところは正されるような感覚がある。簡単に言うと「着心地が良い」ということになるのだが、それでは足らない感じがして、適切ではないと分かっていながら、違和感と言ってしまう程だ。
一見するとシンプルなのだが、目を凝らすと実は恐ろしく複雑にできている。その複雑に計算されたパターンが織りなす、ある意味手品のような緻密な仕掛けが、多様な人の体を文字通り抱擁する。
「OVERCOAT 」の服は、誰にも寄り添い楽しませる、今までになく優しい服である。それと同時に「差別を超える」というなかなか難しい理念を、生地や縫製やパターンといった服の持つ本来の力で実現しようとしている服でもある。誤解を恐れずに言えば、なんとも「尖った」服なのだ。
こんなにも社会にインパクトを与える服なんて、世界中どこを探しても無いと思う。だから、大丸さんがカマラ・ハリス氏の服を仕立てたと聞いても、それは本当に凄いことなのだが、僕は妙に納得してしまう。
僕の勝手な憶測だが、そんな優しくも尖った服が生み出される理由には、大丸さんの今までの人生が影響していると思わずにはいられない。(「Dice&Dice、OVERCOATと出逢う。前編・後編」で大丸さんが半生を語ってくれています。)
そして、聞き苦しいだろうと思いつつも、前半で僕の半生をつらつらと語ってしまったのは、そんな大丸さんの人生と、自分の人生を傲慢ながら重ねてしまっているからだ。
大丸さんの半生は、典型的なヒーローの逸話でもなければ、成り上がりの派手なサクセスストーリーでもない。言ってしまえば、社会から逸れたひねくれ者が、ひねくれたまま、ひときわ輝いているといった感じだ。
そんな大丸さんの素朴な人間性と、その人が生み出す服に、僕は心を奪われて「いつか大丸さんのように輝いてみたい」と珍しく憧れを抱いてしまっているのだ。
父親は最後の微調整を終え、小さく「よし」と言って、僕の首に巻かれたクロスを外した。僕は仕上がりを確認するため、目の前の鏡の中に映る自分を覗き込んだ。そこには大丸さんのような髪型になった僕がいた。
こそばゆい感じと誇らしい感じが同時にわっと襲ってきて、僕は思わず鏡から目線を外した。父親はいつものようにブラシを使い、丁寧な手つきで僕の体から髪の毛を払い落とした。僕は父親に一言「ありがとう」と礼を言った。
藤雄紀
Dice&Dice ONLINE STORE 「OVERCOAT」のページはこちらから
「憧れる」とは、いつかその人のようになりたいと思うことだ。だとすれば、自分と憧れの人との間に、何らかの共通点がなければならない。少なくとも、共通点があると思い込んでいなければならない。
だから僕は昔から、簡単に誰かを「憧れる」ことができなかった。僕には「憧れる」なんて傲慢なことを言う自信がなかった。
小学生の頃、少年野球をやっている友達が、「プロ野球選手に憧れる」と言うのを聞くたび、僕はそれをとても羨ましく思っていた。確かに、その友達とプロ野球選手との間には、野球という共通点がある。だから友達はプロ野球選手に「憧れる」ことができる。しかし、その頃の僕は、そういう世の中のヒーロー達と繋がるための共通点を、何ひとつ持っていなかったのだ。
僕はそんなことをぼーっと考えつつ、父親に髪を切ってもらっていた。僕の実家は「カット倶楽部ウッドストック」という名の理髪店を営んでいる。なので幼い頃から僕の髪を切るのは、いつも父親だ。
僕は今まで一度も父親に「誰々みたいな髪型にしてくれ」と言ったことがない。毎回「あと何センチ短く」などと、細かく注文をして切ってもらっている。考えてみれば、そんな面倒なことをしているのも、きっと僕が「誰かに憧れられない」からなのだろう。「誰々みたいな髪型にしてくれ」なんて傲慢なことを、父親にさえ言えなかった。いや、むしろ父親だから言えなかったのかもしれない。
しかし、今回は父親にある人の写真を見せようと決めていた。そのある人とは「OVERCOAT」のデザイナーの大丸さんだった。僕が人生で初めて、自分を似せたいと思った人だ。この人だったら素直に「憧れる」と言える気がする。僕はそう思い、今まで躊躇していた、写真を見せて髪を切ることを決断したのだ。
父親から「お前はその人に憧れてるのか」と聞かれるかもしれないと思うと、何故か急にとても恥ずかしい感じがした。しかし、決めたことだと、父親に恐る恐るスマホの画面を見せた。父親が「誰この人」と聞いてきて、ドキっとしたが、僕はなんとか平静を装い「デザイナー」とだけ言った。父親はそれ以上何も聞いてこなかった。
パーマをあてながら、父親に渡されたファッション誌のページをパラパラとめくる。だが一向に内容は入ってこない。僕はどうしてこんなに大丸さんに憧れているのか、そのことばかり気になって頭の中がいっぱいだった。考えているうちにぼんやりと、中学生の頃の記憶が蘇ってきた。
僕は体が小さく運動神経が無かったので、入部したバスケ部でも完全にお荷物だった。同級生がみんなボールを使った練習をしている中、僕はひとり基礎体力をつけるため、コート脇で腹筋をさせられていた。
休みの日は友達の家に集まってテレビゲームをした。ウイイレやスマブラにみんな夢中だったが、僕はそこでも活躍出来なかった。誰もが僕とチームになると落胆して「もう絶対負けやん」と次々に悪態をついた。運動神経も無い上に、反射神経も人より劣るのだということを、僕はそこで思い知らされたのだった。
今考えれば、その時唯一僕が友達から注目を集めることができたのが、ファッションだったのかもしれない。
僕の家は、ゲームなどの手頃な遊び道具がない家だったので、仕方なく父親が店で不用になり持ち帰ったファッション誌を読んで暇を潰していた。
年齢的にちょうど色気付いてきて、自然とみんなファッションに興味が向き始める時期だった。そんな中、何故かファッションについてちょっと詳しい僕に、みんなが色々と質問してくるようになった。
いつしか僕の「運動もゲームもできないのろま」というイメージに「でもなんかお洒落なやつ」という付加価値がついて、みんなから一目置かれるようになった。それからは部活で失敗して笑われても、むしろ「おいしい」んじゃないかと思えるようになった。
僕みたいなやつでも、面白い事を知っていれば一目置かれる。ダメな部分があっても、それがプラスに転化する。
ファッションというか芸術というか文化というか、そういう類のものが持っている、不思議な力の効力を、僕はその時初めて体感したのかもしれない。
僕はその時から漠然と、ファッションの道に行きたいと思うようになった。しかし、そう思ったところで、具体的にどうしたらいいのか、その頃の僕にはわからなかった。
僕には、ファッションの世界の人達は、プロ野球選手のような典型的なヒーロー達とは全く違って見えた。そんな世の中の基準から外れたヒーローのことを「憧れる」対象にしていいのか自信がなかった。
ファッションは野球と違い「努力している」という実感が持ちにくい。僕がどんなに真剣だろうとも、学校や親からしたら、それは結局遊びでしかない。
僕は、そんな逸れもののヒーロー達と、ファッションという共通点で繋がっているつもりだったが、それを周りの大人達に力強く宣言するだけの自信を、まだ持つことができなかった。
その調子で高校入学後3年間を過ごし、僕は反対する親に無理を言って、服飾の専門学校へ進学することになった。
僕が進学を決めた専門学校には特待生という枠があった。面接の結果次第で、特待生か普通の学生か決まり、特待生になれれば学費の何割かが免除されるという制度だった。
僕はどうしても特待生になりたかった。ここで特待生になることができれば、今まで遊びだと思われていたものが、僕なりの努力だったと証明できるのではないか。そう僕は思ったのだ。
特待生になるためには、面接の場で自主課題の発表を行う必要があった。早速僕は課題に取り組むべく、母親の使わなくなったミシンを押し入れから引っ張り出し、持っていたデニムパンツを解体してバンダナと縫い合わせ作品を作った。
それだけでは心もとなかったので、もうひとつの課題として、思い当たる洋服屋さんにインタビューをして、データベースを作り、ショッピングガイドにして提出しようと思い立った。
意気揚々と街へインタビューに出かけたが、これがなかなか上手くいかなかった。今になって考えればそんなの当然なのだが、客数や客単価や売れ筋などの、社外秘のような情報を、ズケズケと聞いてくるイタい高校生なんて、鬱陶しいに決まっている。ほとんどの店で門前払いをくらい、なんとか話をしてもらえたとしても、叱られることが多かった。
そんな数日を過ごし、ついにリストアップしていた店は最後の一軒になった。その店はダイスアンドダイスだった。
ダイスは僕の中では別格の店だった。「憧れる」なんて軽々しく言えない。それはもはや畏怖するような存在だった。
店構えも働いているスタッフの雰囲気も他とは全然違う。いつも買い物をするだけで汗だくになっていた。
その日も緊張のあまり、店の前を行ったり来たりして、何度もそのまま帰ろうかと思った。
しかし、特待生になるためにはこの試練を超えなければならない。そう自分に言い聞かせて、決死の覚悟で店中へ飛び込んだ。滝のように流れる汗を押さえながら、僕はスタッフの人にインタビューの概要を説明した。
すると意外にも「全然いいよ」と言って快くインタビューを受けてくれた。インタビューだけでなく、親身になって自主課題の相談にも乗ってくれ、最後に「頑張ってね」と声をかけてもらえたのを、今でもはっきりと覚えている。
振り返ると、この時の出来事は僕の人生の中で、とても大切な経験だったように思う。誰から言われるよりも嬉しい「頑張ってね」だった。初めて努力が認められたような感じがした。
少なくとも、いつかこんな店で働いてみたいと、僕が強く思うようになったきっかけであったのは言うまでもない。
僕はやっと完成させた自主課題を持って専門学校の面接の場に挑んだ。結果は不合格だった。
高校の内申点が高くないと特待生にはなれないということを、僕は後から知った。
普通の学生として通い始めることになった専門学校は、どうしても身が入らなかった。今思えば僕が浅はかだったのだろうが、その時は、無意味な声出しや服のたたみ方を、わざわざ学校で学ぶことに、何のリアリティも感じなかった。
僕は親に相談もせず、一年も経たないうちに、学校を辞めてしまった。純粋な憧ればかりを追い求めるあまり、現実が見えなくなって、自分でも収拾がつかなくなっていた。
親と折り合いがつかなくなって、実家に居づらくなり、半年間程ふらふらと公園で寝泊まりする生活を送った。
なんとかなるだろうと思っていたが、実際はなんともならなかった。どうしようもなく腐りかけていた時、知人から急な誘いを受けた。「ダイスで働いてみらん?」僕は二つ返事で「はい」と答えた。
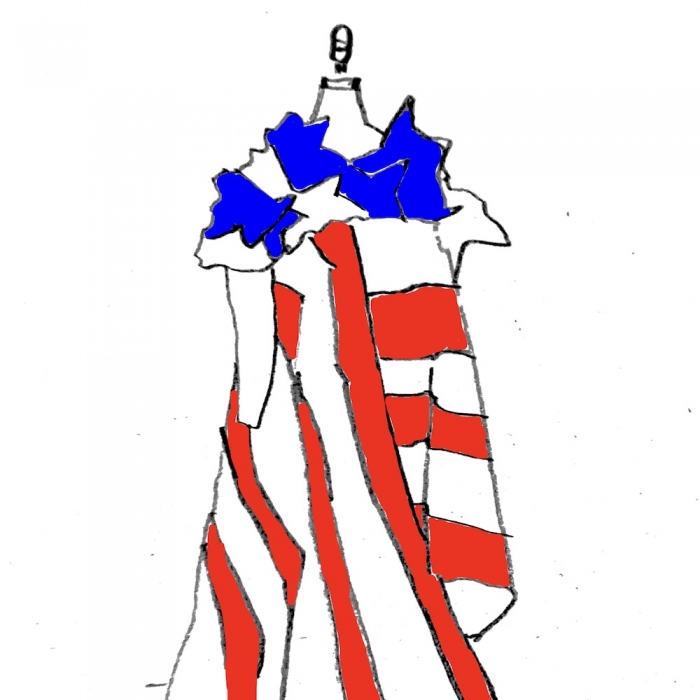
憧れの場所で働き始めてかれこれ10年。その間、僕は沢山の素敵な服と出会った。中でも最も衝撃を受けたのが大丸さんの作る「OVERCOAT 」だった。
「OVERCOAT 」の服を初めて着た時、僕は強烈な違和感を感じた。いつもは窮屈なところに、空間ができていることに気がつく。いつもは沿わないところに何故か生地が沿ってくる。緊張しているところは程よく緩み、逆に緩んでいたところは正されるような感覚がある。簡単に言うと「着心地が良い」ということになるのだが、それでは足らない感じがして、適切ではないと分かっていながら、違和感と言ってしまう程だ。
一見するとシンプルなのだが、目を凝らすと実は恐ろしく複雑にできている。その複雑に計算されたパターンが織りなす、ある意味手品のような緻密な仕掛けが、多様な人の体を文字通り抱擁する。
「OVERCOAT 」の服は、誰にも寄り添い楽しませる、今までになく優しい服である。それと同時に「差別を超える」というなかなか難しい理念を、生地や縫製やパターンといった服の持つ本来の力で実現しようとしている服でもある。誤解を恐れずに言えば、なんとも「尖った」服なのだ。
こんなにも社会にインパクトを与える服なんて、世界中どこを探しても無いと思う。だから、大丸さんがカマラ・ハリス氏の服を仕立てたと聞いても、それは本当に凄いことなのだが、僕は妙に納得してしまう。
僕の勝手な憶測だが、そんな優しくも尖った服が生み出される理由には、大丸さんの今までの人生が影響していると思わずにはいられない。(「Dice&Dice、OVERCOATと出逢う。前編・後編」で大丸さんが半生を語ってくれています。)
そして、聞き苦しいだろうと思いつつも、前半で僕の半生をつらつらと語ってしまったのは、そんな大丸さんの人生と、自分の人生を傲慢ながら重ねてしまっているからだ。
大丸さんの半生は、典型的なヒーローの逸話でもなければ、成り上がりの派手なサクセスストーリーでもない。言ってしまえば、社会から逸れたひねくれ者が、ひねくれたまま、ひときわ輝いているといった感じだ。
そんな大丸さんの素朴な人間性と、その人が生み出す服に、僕は心を奪われて「いつか大丸さんのように輝いてみたい」と珍しく憧れを抱いてしまっているのだ。
父親は最後の微調整を終え、小さく「よし」と言って、僕の首に巻かれたクロスを外した。僕は仕上がりを確認するため、目の前の鏡の中に映る自分を覗き込んだ。そこには大丸さんのような髪型になった僕がいた。
こそばゆい感じと誇らしい感じが同時にわっと襲ってきて、僕は思わず鏡から目線を外した。父親はいつものようにブラシを使い、丁寧な手つきで僕の体から髪の毛を払い落とした。僕は父親に一言「ありがとう」と礼を言った。
藤雄紀
Dice&Dice ONLINE STORE 「OVERCOAT」のページはこちらから